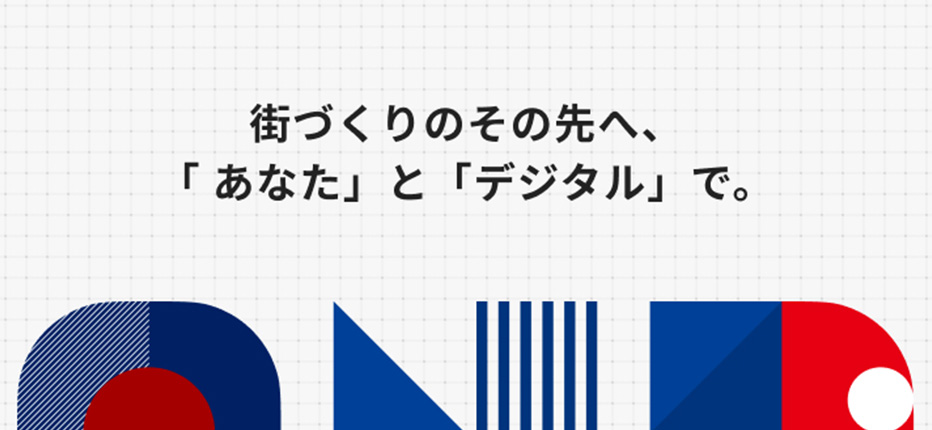そして、〈越境〉は
続いていく。
周 潔
Kiyo Zhōu
2017年入社
前職:建設会社



その夕刻、地上136mを吹く風が心地よかった。上棟式を終えたばかりの超高層マンションの屋上からは、遮るもののない眺望が遥か遠くまで続いている。「やあ、周さん」と声をかけられ、一緒に工事をしてきた職人たちが家族連れで集まってくる。工期中にも何度か、運動会や鍋パーティーなどのイベントを開いては、職人どうしの連帯感を深めてきた。工事を円滑かつ安全に進める狙いもある。
周がこの現場にやってきたのは、前職の建設会社に入社後間もない頃だった。外国人女性としては社内初となる現場監督として、ピーク時には約600人もの職人の工程を管理した。朝のラジオ体操に続いて行う朝礼では、ヘルメットに作業着姿の周がお立ち台に上り、前夜に暗記した作業内容を説明する。人前で話すのが不得手なため、苦痛で仕方なかった。もう一つ、始業前にはルーティンがある。顔と名前を必死に覚えた約30名の職長たちの、好みの缶コーヒーを持参して控え室に走る。雑談をしながら、それぞれの進捗状況を聞き出すのだ。
何万本にもおよぶ鉄筋の太さや長さを図面をもとに確認する作業は、周に一任されていた。ワンフロアの工期は5日間、毎日が時間との勝負である。それでも、周は作業用エレベータを使わずに、1階から最上階まで階段を毎日2〜3往復した。資機材を運ぶ職人たちを優先させるためだ。ようやく、この屋上イベントの日に、乗り心地を確かめながらエレベータで昇ることができた。現場では、日本の文化や職人の世界に戸惑うこともあれば、興味深いこともあり、刺激的で密度の濃い社会人一年目だった。そんな日々を祝うかのように、近くで花火大会がはじまり、夜空と周たちの顔を照らしていた。
******

周は中国河南省の洛陽市で生まれ育った。幼少期から続けていたピアノを音大で学びたいと思っていたが、両親から理系への進学を強く勧められて断念した。そんなときに手にしたのが、安藤忠雄の著書だった。理系の中でも建築なら、芸術という括りで音楽に近いかもしれない。ボクサーの経歴を持つ安藤忠雄が、まったく異なる建築の世界で成功していることに感じるところもあった。ピアノから転向する自分と、どこか重なり合うように思えたのだ。
日本の大学で教鞭をとる叔父の勧めもあり、周は日本に留学して建築を学びはじめた。だが、同級生たちと自分の才能の差を痛感する。院まで進んで自分なりに踏ん張ってはみたが、どうしても立ちはだかる壁があった。建築家は諦めるしかなさそうだ。では、自分はなにがしたいのだろう。答えが見つからないまま、就活の時期を迎えた。留学生たちに人気の外資系企業なども回ったがピンとこない。最終的には教授が推薦してくれたゼネコンに決めた。
ゼネコン内の研究所を勧められたものの、じつは周は研究には興味がなかった。面接でも正直にそう伝えると、面接官は言った。「それじゃあ、まずは現場監督としていろんな経験を積んだらどうかな?」。その言葉を受け入れて、現場監督を2年間務めたあと、コスト管理、経営企画へと異動した。とにかく与えられた目の前の仕事に正面から向き合い続けていた。



経営企画部で3年目を迎えたある日、周はさまざまな会社の企業満足度調査をまとめる作業を行っていた。上長から与えられていた、「社員の質を上げるにはどうすればよいか?」という経営課題を解決する糸口になると考えたのだ。就活生用の口コミサイトなどを見ながら、各社の点数をリスト化していく。大半の会社は3点程度、自社は3.67点だったが、1社だけ5点満点の会社があった。「えっ、この三井不動産って、なぜこんなに満足度が高いのだろう?」
答えを求めて、周はさらにさまざまなサイトから情報を集めた。すると、三井不動産の社風を知るにつれ、「本当にいい会社なんだ」「こんな会社で働いてみたい」という気持ちが膨らんでいく。これまでもやり甲斐や楽しさは感じてきたが、一つだけ引っかかりがあった。外国人である特性を生かして、いつかは海外の仕事をしてみたいと考えていたが、いまの会社では叶えられそうにないということだ。だが、海外展開を推進している三井不動産ならチャンスがあるのではないか。ピアニストと建築家は断念したが、もうこれ以上、自分の道を諦めたくない。
念願の三井不動産の面接に合格した周だったが、入社前にして不安が大きくのしかかる出来事があった。少しでも早く会社に慣れるようにと、同い年の社員たちとの会食の場を人事部が設けてくれたのだが、彼ら彼女らの放つエネルギーに圧倒されてしまったのだ。自分がどこか場違いなところにいる気持ちになり、やっていける自信がまったく持てない。入社後は都心部の商業施設を開発するアーバン事業部に配属されたが、さらに現実を突きつけられた。溌溂と働くチーム内の1〜2年目の社員たちにも敵わない。自分の欠点ばかりに目が向いてしまう毎日だった。
******

入社から約半年経った頃、周はさらなる試練にさらされる。銀座の商業ビルの立て替え案件を巡って、施主兼オーナーの要望に添った設計プランの検討を任されたが、さまざまな制約により、地下1階の実効面積が要望よりどうしても狭くなってしまう。設計事務所にも確認した上で、実現不可能であることを伝えた周に、施主は言い放った。「お前は、もう、いらない。ここには二度と顔を見せないでくれ」。そこまで激しく怒られるのは人生でも初めての経験で、衝撃を受けた。ゼネコン時代に一級建築士・積算士・施工技士などの資格を取得していた自負もある。自分のなにがいけなかったのだろう……。
いずれにしても、状況を報告しなければならない。重要顧客なだけに叱られる覚悟で臨んだ周に、上司は言った。「当然のことを施主に話したまでだよな。100なら100全部を正確に伝えないと、施工現場はとんでもないことになるから、それはそれでいいんだ。でもさ、オレが今回の周の立場なら、一度に100は否定しない。向こうから『これは不可能だね』という言葉を引き出せるよう、相手の反応を見ながら10ずつジワジワと伝えるかな」。失敗を責めることなく、対案まで示してくれるなんて……。周は感激した。だから誰もが萎縮することなく壁を越えていき、次の挑戦へと果敢に立ち向かえるのだ。前職時代に調べた企業満足度の高さは、こうしたところにも起因するのだと深く頷いた。この会社で、もっと頑張っていこう。
その後、東京・大阪・名古屋の繁華街の商業ビルや東京五輪の選手村の施設などを次々と手がけた。産育休暇を挟んで異動したビルディング事業二部では、駅前大規模開発案件に携わっていく。あるとき、周はハッと気付いた。設計会社やゼネコンとの打合せの場に、馴染んでいる自分がいる。対等に意見を交わし互いの知見を高め合えている……。大学で学んだ建築学、前職で経験した現場監督、この会社で担当した商業施設やビルの開発など、これまで進んできた道は筋の通った一本ではなく、バラバラの寄り道だったと思い込んでいた。だが、こうして開発という舞台に立ってようやく見えてきた気がする。じつは繋がりのある道を歩んでいたのだ。


2020年の秋、社内の事業提案制度の募集が告知された。社員が自らのビジネスアイデアを会社に提案し、有望な案件を新規事業化していく制度で、2018年の制度運用開始以来、過去3件が実際に事業化されている。これはチャンスかもしれない。不得意なプレゼンテーションに挑めるし、自分の知識やスキルのレベルが客観視できると捉えたのだ。コロナ禍に見舞われたときに考えていた、ブランド事業者の売上を伸ばすプランを提案してみてはどうだろう。頭の中ですでに練り上げていたせいか、気がつくとわずか2日で書き上げていた。その勢いのまま臨んだプレゼンは経営陣の心を動かし、周の提案は見事に承認された。2021年秋には事業化の検討に向けて、ビジネスイノベーション推進部と商業施設運営部への兼務辞令が下りた。
在日中国人インフルエンサー数十人の協力を得て、日本国内のアパレルやコスメの商品をライブ配信して売り込む。中国市場へのライブコマースが周の描いている新規事業の大枠である。国内市場向けはすでに社内でスタートしていたが、自分はかねてからの海外への想いと外国人であることを武器に、越境ビジネスの可能性を拡げたいと考えたのだ。インフルエンサーの開拓、国内ブランドとの交渉、配信スタジオの設計、法律面の調査や契約書づくり、サービス名の商標登録など、一つひとつのスキームを進めていった。
ライブ配信によって、まだ知名度の低いブランドは成長の足がかりを得て、やがてはテナントというリアルな売場に展開していく可能性がある。すでに知名度の高いブランドにとっては、販売チャネルの選択肢が増える。つまり、テナント事業と新規事業には相乗効果があると、周は考えている。この事業が成功するかどうかは正直なところわからない。失敗したとき、次に自分がなににチャレンジするのかもわからない。だが、どんな将来になるか予想ができないからこそワクワクできる。自分はなにを越えて、どこに行くのか、楽しみでならない。
******
仕事中はスピード感に追いつくのがやっとで、自分を省みる時間はなかなかとれない。だから、1年半の産育休は、三井不動産での2年間を振り返るいい機会になった。その間、上司と2回面談した。
「周さんは、ここをもっと伸ばせばいい。まずはそこから一歩ずつ積み上げていけばいいんじゃないかな」
スムースに復帰できたのも、この上司の言葉があったおかげだ。誰にだって得意、不得意はある。全部を伸ばそうと無理する必要なんてないんだな。そう思うと、休暇明けの仕事への気負いも自然に消えた。
じつは産育休の大半は、動画サイトを見て過ごしていた。コミュニケーションの際に日頃から必要性を感じていた、日本語での雑談力を身に付けたい。中国から日本にやってきて約17年、ずっと持ち続けてきた苦手意識を越えていきたいと思ったのだ。こんなときには、こう答えるといいんだ。こう言われたら、こうかわす手があるんだ。こんな会話には……。ついつい、続けて何本も視聴してしまう。復帰した周に、上司は笑顔でこう言った。
「あれ、周さん、なんだか日本語うまくなったね」
いままで下手だったってことですよね……と、冗談っぽく返そうかな。そう思いながら、周の心は躍っていた。


All Rights Reserved.