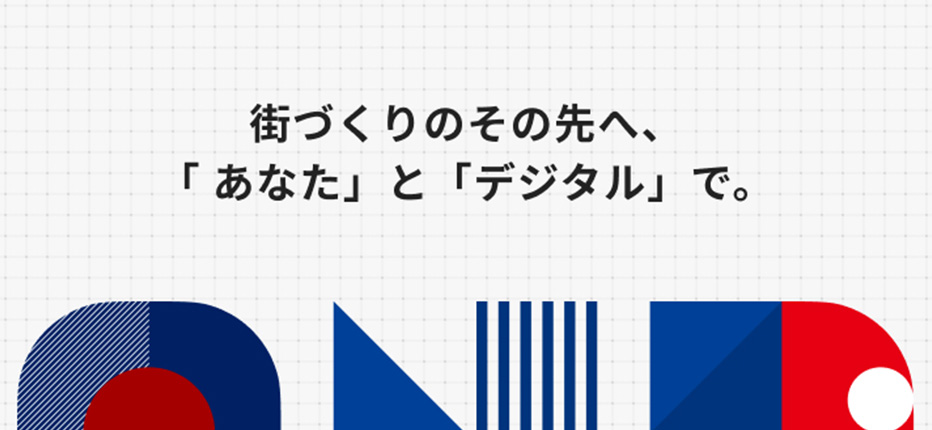1/30秒に賭ける世界から、
100年を繋いでいく世界へ。
柿野 陽
Yo Kakino
2021年入社
前職:放送局



日本中の野球ファンが固唾を呑んで、仙台からのテレビ中継を見守っていた。日本シリーズ第7戦のマウンドには、シーズン24勝を上げ、のちに大リーグで活躍するエースがリリーフに立っている。「あと一人!」コールがホームグラウンドに巻き起こる中、局本社にいる柿野は、違った意味でハラハラドキドキしていた。
その瞬間に絶妙のタイミングで、優勝を告げるテロップを出さなければならない。誤って相手チーム用のテロップを出したりしたら一大事だ。過去に何度か始末書を書いたこともあるが、今回はそれどころでは済まないだろう。エースが最後の打者を抑えたと同時に、一斉に選手たちがマウンドに駆け寄り、球場に花吹雪が舞う。
よし、いまだ! 歓喜の光景に、柿野がスイッチングしたテロップが映像に被さる。〈楽天イーグルス、日本一おめでとう!〉。安堵する間もなく、やがて優勝監督インタビューが始まる。「東日本大震災で傷ついた人たちに勇気を与えたかった!応援ありがとう!」。7か月にわたるシーズンの1試合1試合を闘い抜いてきた選手たちがそうであったように、自分たちも中継チーム一丸となって日本中の視聴者に感動の瞬間を届けられたんだ、と柿野はしみじみ思った。2013年11月3日のことである。
******

海側の化学プラント群と山側の自然に挟まれた、三重県四日市で柿野は生まれ育った。県内最大の人口を誇る街だが、少し退屈さを感じてしまう土地でもあった。一人っ子だったため、夕方に友達と別れて家に帰ったあとは、自分で工夫して独り遊びをすることが多かった。そんな生い立ちもあってだろうか。たくさんの人たちで賑わう、華やかな大都会への憧れが強かった。
その憧れはやがて、たくさんの人にリーチできる華やかな世界に関わりたいという想いに変わり、六本木に本社を置く放送局に就職し、スポーツ局に配属された。名だたるアスリートたちとの公私にわたる交流やポジティブな空気、人の感情に深く入り込んで記憶に残るスポーツの魔力に触れ、刺激的な毎日を送っていた。現場に入ると泥臭い仕事も少なくなかったが、「なんて素敵な仕事をさせてもらっているのだろう」と心は満たされていた。編成局に異動してからも、自由の利くCS放送の深夜枠で趣味を生かした麻雀番組を制作するなど、大都会のど真ん中で仕事を楽しんでいた。
そんな折、コロナ禍の在宅ワーク中に何気なく開いたSNSで、友人が「いいね!」を押していた広告に目が留まった。三井不動産の採用サイトだった。アクセスして読んでいくと、心のどこかに刺さっていた小さな棘が、チクッと疼いた。自分は多くの人にスポーツの試合や情報を届けているが、その向こう側のテレビの前にいる人の顔は見られない。“画面の向こう側”の視聴者は一体どんな表情でテレビを見ているのだろう。視聴率という数字だけでは、視聴者が本当に楽しんでいるのかどうか、本当のところがわからない。だが、このサイトに書かれている街づくりの仕事なら、そこに集う人たちの顔を直接見て、その反応を五感でキャッチできるのではないか? 緊急事態宣言の制限が解除され、閑散としていた街に人々の賑わいが戻ってきた光景も、柿野の背中をグイッと押した。自分はもっと、直に、たくさんの人たちと関わっていきたい──。



三井不動産に転職した柿野は、日本橋街づくり推進部に配属された。地元の人たちと一丸となり、さまざまな角度から日本橋をより魅力的な街へと進化させていく部署である。その中でも柿野が担当しているのは、産学官のプレイヤーを対象に、宇宙・食といった産業領域におけるオープンイノベーションを、デベロッパーの立場から推進していく「産業創造」の役割だ。
日本にイノベーションを起こすスタートアップと歴史ある日本橋の文化・伝統をいかにコラボさせて、未来に向けた日本橋ならではのアクションを発信していけるか──。その答えを常に探して回っていた柿野に、ある出会いが訪れた。国主導のフードテック協議会にも参加しているVCとの打合せの中で,大豆や昆虫などの代替食材を開発するスタートアップを数社紹介されたのだ。その1社に柿野は、これだ!と直感した。「えっ、コオロギ! これ面白そうじゃないか!」
商品化はできるが、どうしたら美味しく食べてもらえるのか模索しているスタートアップと、日本の食文化を創造してきた日本橋の老舗飲食店をコラボレーションさせれば、イノベーションが生まれるのではないか。スタートアップは乗り気を見せたが、老舗飲食店の反応を思うと、柿野は不安だった。かつてテレビ局時代を過ごした六本木は、ITベンチャーが集まるエネルギッシュで革新的な街だが、老舗が集まる日本橋となると、おそらくは保守的な人たちも多く、一蹴されるのではないか……。
******

日本橋には、老舗飲食店の若旦那たちによる三四四(みよし)会という組合がある。これまでの三井不動産の街づくりにおいても、常に綿密な連携をとってきた。その窓口になっている同僚に、柿野は提案のコンセプトを話した。健康志向や環境意識が高まる中で、新たなタンパク源として注目される代替食品。歴史ある老舗の店たちが新しい食材を使って、未来の食を考える──。同僚は笑顔でうんうんと頷きながら言った。「なるほど、面白いな。今度の会合で話してみるよ」。
ソワソワドキドキしながら過ごしていた数日後、同僚から連絡が来た。「ぜひ挑戦してみましょうって快諾してもらえたよ。良かったなー」。柿野はふと、部長から口癖のように聞かされていた話を思い出した。「日本橋はいまでこそ昼夜、休日も賑わう街になったけど、バブル崩壊後は活気を失った時期もあったんだ。土日や夜遅くは開いている店も少なくて、人通りもまばら。今では想像できないくらい寂しかったことを思い出すよ」。
そこで、「このままじゃいけない。文化や伝統を残しつつ、再び日本橋に賑わいを獲り戻そう」と、官民地元一体となって取り組み始めたのが、〈日本橋再生計画〉だった。中でも三四四会の若旦那たちは、「食」の面から新しいことにもどんどん挑戦し、街の再生に取り組んでいる。そうした日本橋の風土を、入社1年目の柿野はまだ把握しきれていなかった。だから、不安が先走ってしまったのだ。


2022年の春、9回目となる「SAKURA FES NIHONBASHI」が23日間にわたって開催された。テーマは「もう一度、美味しいでつながろう」。コロナ禍で様変わりした飲食という当たり前の行為が、いかにかけがえのないものだったか。そのことにあらためて向き合い、新しい食の時間を体験してもらいたい。今回のイベントには特にそんな想いが込められている。会期4日目にはまん延防止等重点措置も解除され、夜にはライトアップされた桜並木の下を、大勢の人たちが行き交った。
4月2日・3日の昼前、メイン会場となるCOREDO室町テラスの大屋根広場に柿野はいた。スタートアップ企業と老舗日本料理店との共創による弁当販売のブースに行列ができている。その中の一品、〈コオロギ茶碗蒸しのグリーンミートあんかけ〉は、試行錯誤の末に完成したもので、柿野自身も「え? コオロギって、こんなに美味しいの?」と驚くほど絶妙な味に仕上がった。名付けて〈つながる未来弁当〉は、かつての同業者であるマスコミの食いつきも上々で、多くのメディアにも取り上げてもらった。
もし自分が取材クルーなら、どんな編集をするだろう。テレビ局時代は、1/30秒というフレーム単位でタイミングを工夫し、視聴者に与える印象を考える仕事をしていた。対照的に、いまの柿野が夢中になっているのは、日本橋の伝統を未来へと繋ぐ、100年単位の仕事である。テレビ番組は短いスパンで改編できるが、一旦始めた街づくりは決して後戻りはできない。それだけに、自分たちが腹を括れるまで徹底的にさまざまな視点から検討を繰り返し、繰り返し尽くす。前職時代と変わらないのは、チーム一丸となって一気に動かしていくこと。そして、どんなにタフな局面であっても、もっと面白くしよう、もっと楽しくしようという気持ちだ。それはもちろん独りよがりであってはならない。その土地に暮らす人の表情や言葉から、想いを肌感覚で受け止め、調和させていくことが大前提になる。
******
ある晴れた日、三井不動産と同じ年にあたる80歳の地元住民のAさんと、現在の日本橋川を覆う首都高速道路の地下化計画に話が及んだ。橋や川縁から見上げると、大きな空が気持ちよく広がっている。そんな光景を頭にイメージした柿野に、Aさんがこう言った。
「その日が楽しみでならないね」。「はい。早く見たいです!」
完成予定は2040年、そのとき100歳を超えることになるAさんの目は、日本橋の将来を見つめ、キラキラと輝いている。柿野は想いを新たにした。
この街を愛する人たちの心意気にもっと応えていきたい。日本橋はもっと素敵な街に変わっていける。100年単位の街づくりは、まだ始まったばかりだ。


All Rights Reserved.